同じ失敗を繰り返さないための「思考」と「デジタルマーケティングの定石」|Synergy!20周年カンファレンスレポート3
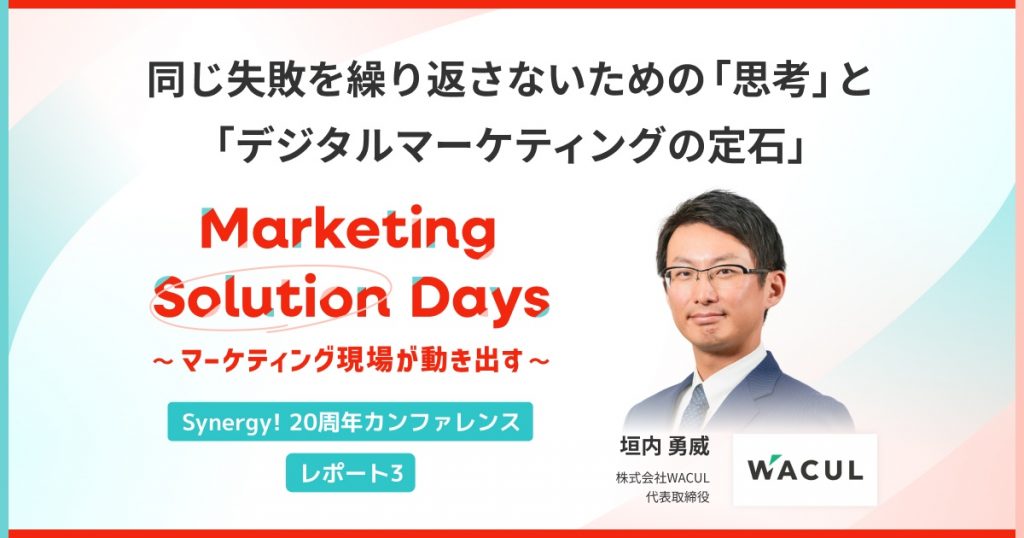
2025年6月25日から26日にかけて、シナジーマーケティング(以下、当社)は、マーケターの課題解決に徹底的に向き合うカンファレンス「Marketing Solution Days〜マーケティング現場が動き出す〜」をオンラインで開催しました。
本カンファレンスでは、マーケターが抱える課題を解決するアプローチを通じて、マーケティング現場を前進させるための実践的な方法を提示することを目的に、2日間で23セッションをご提供。おかげさまで2,700名を超える方々にお申し込みいただき、盛況のうちに終了いたしました。
その中から、株式会社WACULの代表取締役 垣内勇威氏をお迎えした基調講演「デジタルマーケティングの定石 ~なぜ同じ失敗を繰り返すのか?マーケターの思考をアップデートする~ 」の様子をお届けします。
登壇者

垣内 勇威 氏
株式会社WACUL
代表取締役
東京大学卒。ビービットから、2013年にWACUL入社。改善提案から効果検証までマーケティングのPDCAをサポートするツール「AIアナリスト」を立ち上げる。2019年に産学連携型の研究所「WACULテクノロジー&マーケティングラボ」を設立。研究所所長および取締役CIO(Chief Incubation Officer)として、新規事業や新機能の企画・開発およびDXコンサルティング、大企業とのPoC(概念実証)など、社内外問わず長期目線での事業開発の責任者を務めてきた。2022年5月に同社代表取締役に就任。
※部署名・役職は取材当時(2025年5月)のものです
本セッションのポイント
- デジタルマーケティングの役割を意識し、デジタルの強み・弱みを理解したうえで目標に対して適切な活用を行う。
- デジタルマーケティングの定石は18種類あるが、大別すると「Web完結型」「Web to 営業担当型」に分かれる。まずは難易度の低い後者から着手すると良い。
- 全社的なデジタル化を進めるためには、営業をはじめとする他部門の”気持ち”への寄り添いが不可欠。「Quick Win」を提供し、信頼関係を構築する。
昨今の多様化する市場で企業が持続的な成長を遂げるには、デジタルマーケティングをはじめとするデジタルの活用が不可欠です。一方で、デジタル技術は導入するだけで成果が上がる万能なツールではありません。その強みと弱みを理解し、目標達成に向けて最適な戦略を実行することが成功の鍵となります。
本レポートでは、デジタルの特性やデジタルマーケティングの定石に加え、実践的な活用事例、組織全体のデジタル推進を成功させるためのポイントについてご紹介します。
デジタルへの幻想を捨て、成果を掴む現実的なアプローチとは
「最新のデジタル技術を駆使すれば、ビジネスモデルを変化できるのでは」―― このような期待を抱く企業は少なくありません。しかし、20年以上にわたってデジタルコンサルタントの第一人者として活動されてきた垣内氏は、「それは幻想であり、デジタル技術は万能ではない」と明言。
デジタルマーケティングを深く理解せずに失敗したプロジェクトの具体例を挙げ、その根底にある「デジタルへの過度な期待」の危うさを指摘しました。「AIに大量のデータをインプットすれば良い示唆が得られるのではないか」と考える方もいますが、現状では、「会員ランクが高いほど、売り上げが高い」といった当たり前の結果や「ビールとおむつは一緒に買われる」といった因果関係を立証できず施策に落とし込めないようなアウトプットになりがちです。「現段階のAIは単純作業の自動化ができるレベルで、デジタルマーケティング初心者が成果を出すために活用できるものではない」と垣内氏は語られました。

「デジタルにできること(強み)とできないこと(弱み)の線引きが重要。髪を切るハサミで石を切ろうとしても、当然ながら成果は出ない」と垣内氏は語り、その強みと弱みに言及しました。
- デジタルの強み
- 高い費用対効果とストック性
一度実施した施策で集めた顧客(リード)には、継続的にアプローチが可能。作成したコンテンツも資産(ストック)となるため、中長期的に見ると費用対効果が高い。 - 低ランニングコスト
人間が介在する部分が少ないため、運用にかかるランニングコストを抑えられる。 - 低コストで顧客アプローチ
メールやSNSなどを活用することで、費用をかけずに顧客へのアプローチが可能。
- 高い費用対効果とストック性
- デジタルの弱み
- 態度変容の難しさ
人間が介在しないセルフサービスチャネルであるため、時間をかけて説得するといったことができず、顧客の態度変容を促す力がない。 - 集客の即効性・爆発力不足
テレビCMは一瞬で1,000万人規模にリーチし、投資直後に集客できるフロー施策であるのに対し、デジタルで毎月10万人の閲覧者を集めるためには内容の濃い記事が300本ほど必要になるなど、集客の即時性・爆発力がない。
- 態度変容の難しさ
上記を踏まえ、デジタルマーケティングの役割について垣内氏は、「デジタルで対応できる仕事を人間の手から奪い、コストカットをすること」「以前のマーケティング手法からより成果の上がる新しい手法に置換すること」だと解説されました。冒頭で述べたように「ビジネスモデルの抜本的な変革」ではなく、まずは成果を出すために足元を固めること、つまりコスト削減や業務効率化に注力すべきとの考えです。
成功へのロードマップ!デジタルマーケティングの”定石”で課題を打破する
垣内氏は、「成果を出すためのデジタルマーケティングの定石は、18種類しか存在しない。そしてそれは、『Webのみで完結する型』『Webでアプローチしたあとに人間(営業)につなぐ型』の2種類に大別される」と述べ、それぞれの特徴を解説されました。

- Web完結型
デジタル施策のみでリード獲得から態度変容の促し、受注までもっていくモデル。デジタルが苦手とする顧客の態度変容の促しをしなければならないため、比較的難易度が高い傾向にある。
- Web to 営業担当型
デジタル施策でリードを獲得したあと、営業がコミュニケーションを取って受注につなげるモデル。人間が介在するため社内調整や体制構築が必要になるが、営業による態度変容の促しができるため、比較的難易度は低い傾向にある。そのため、初めてデジタルマーケティングに着手する場合は、こちらから始めると良い。
続いて、比較的実施しやすいWeb to 営業担当型に焦点を当て、「リード獲得の4ステップ」を紹介されました。

1. CV(コンバージョン)障壁設計
リード獲得において最も重要視すべきは、コンバージョンの障壁設計。資料請求のような「クローズドクエスチョン(選択肢で回答)」はボタンクリックの障壁が低く、問い合わせのような「オープンクエスチョン(自由記述で回答)」はハードルが高い傾向にある。
これらの設置の組み合わせ次第で、問い合わせ数が最大で3倍程度変わることもある。ただし、障壁を下げるほど顧客の質(サービスへの興味関心度合い)は下がるため、このトレードオフをどうコントロールするかが重要。
2. 全ページゴール直行
WebサイトやSNSなどのリンクは、すべて最終的なゴール(資料請求フォームなど)に直行させると良い。デジタルは顧客の態度変容を促すことが苦手で、複数のページを経由させたとしても顧客の購買意欲を高めることはできない。実際に調査でも、最終的なゴールに直行させることでCVが伸びる傾向にあると判明している。
ファーストビューにゴールを置くことで、問い合わせ数が1.6倍に増えた事例もある。長いLPは不要で、ファーストビューで完結しているように見せると有効。そのため、Webサイトの構造は、「ピラミッド構造」ではなく「LP × CVの集合構造」が適切。流入元ごとに最適な入り口ページとCVを用意し、最終的なゴールに直行させる構造にすると成果が出やすい。
3. 外部集客
「トリプルメディア(オウンドメディア、ペイドメディア、アーンドメディア)」を意識する。なかでも、コンテンツをストックし続けられるオウンドメディアは、中長期的な費用対効果に優れるため、効果的。一方で、自社の商材とはあわないメディアの活用は避ける。

4. リストのニーズ検知
獲得した顧客リストに対してメールなどで継続的に接触することで顧客のニーズを検知し、ホットになったタイミングで営業からアプローチをかけることが重要(営業担当による「定期連絡」の代替)。メールは基本的に無料で配信でき、電話やLINEと比較しても顧客からのネガティブな反応が少ないため、活用すると効果的。
メールは、「顧客にコンテンツを読んでもらうこと」ではなく「ニーズ検知のために、継続して接触すること」という意識で配信する。文字量や画像の有無はクリック率に影響しないという調査結果もあるため、メールの作成に必要以上に時間をかける必要はなく、基本的に読まれないという前提でOK。「興味のある人にだけ読んでもらえれば良い」と割り切る。
デジタル変革を阻む「感情の壁」をQuick Winで突破する
多くの企業でデジタル化が進まない最大の理由は、「営業部門をはじめとする他部門の気持ちに寄り添えていないから」だと垣内氏は語られました。
営業部門から見ると、前述のデジタル施策は「営業の仕事の邪魔をしている」とネガティブに映ってしまう危険性があります。営業部門の協力が得られないことで、デジタルマーケティングが局所的な最適化に陥ったり、バズワードに飛びついて費用をかけたわりに成果が出ない「廃墟プロジェクト」を生み出してしまうなどといったことが、往々にあるとのことです。

垣内氏は、この状況を打破して部門間で連携するためには、「Quick Win(短期的な成功)」の提供が不可欠だと解説。具体的には次の通りです。
■Quick Winの一例
- 営業部門にとって「美味しい案件」となるアポイントメントの条件を部門長に直接ヒアリングを行い、実際にそのような案件を取ってくる。
- マーケティング部門にIS(インサイドセールス)チームを立ち上げてコールを行い、自分たちでアポイントメントを獲得する。
- 営業部門と連携してLP(ランディングページ)や広告を作成し、場合によっては営業に同行して顧客訪問を行ったうえで施策に関するフィードバックをヒアリングし、改善する。
垣内氏の講演は、デジタルマーケティングの本質を再認識させるものでした。単に新しいビジネスモデルを追求するのではなく、まずは既存のマーケティング手法をデジタルで最適化し、コスト削減と業務効率化を図るという原点に立ち返ることの重要性が強調されました。そして、この基盤を固めた上で、他部門へ「Quick Win」を提供することこそが、全社的なデジタル化を促進し、顧客ニーズを確実に成果へ繋げる実践的なアプローチであると締めくくられました。
本セッションは、デジタルマーケティングへの過度な期待を排し、その特性を理解した上で「定石」に基づいた戦略を実行することの有用性を示唆しました。また、部門間の連携を深めるための「Quick Win」がデジタル変革を成功に導く鍵となる、という示唆に富んだ内容となりました。

本セッションレポートのほかにも、別のセッションに焦点を当てた記事を公開しています。ぜひあわせてご覧ください。
MONJUのクラスタリングと生成AIで挑む 中川政七商店のブランドコミュニケーション戦略 | Synergy! 20周年カンファレンスレポート1
登壇:株式会社中川政七商店
経営企画室兼MONJUプロジェクト MONJUプロジェクトマネージャー 中田 勇樹 氏
株式会社MONJU
Sales & Marketing Director 後迫 彰 氏
生成AIを活用して顧客理解から新たな価値を創造するためのポイント | Synergy! 20周年カンファレンスレポート2
登壇:株式会社オージス総研
コンサルティングサービス部 新価値創造チーム リーダー 海老原 利恵 氏
シナジーマーケティング株式会社
クラウド事業部 サービスデザインG マネージャー 阪口 奨
▶︎カンファレンスレポートを読む
当社は今後も、お客様の理想実現に向けて、システム導入はもちろんのことさまざまなご支援を続けてまいります。成功事例やノウハウ・知見をお伝えするウェビナーの実施、展示会への出展なども随時行っていますので、ご期待いただけましたら幸いです。
▶︎デジタルマーケティングに関するウェビナーや展示会の情報、サービス資料などのお問い合わせはこちら
(制作/編集:経営推進部 ブランドマネジメントチーム)