
生成AIの台頭は、日本のビジネス界に「業務プロセスや働き方」の抜本的な変革を迫っています。市場の多様化や少子高齢化が進む日本において、AI活用は単なる業務効率化ではなく、企業存続に向けた競争力強化の要になりつつあります。つまりAIを適切に活用できるデジタル人材を育てることは、企業の未来を左右する重要な投資といえます。
このような背景から、シナジーマーケティング(以下、当社)は、LINEヤフー様、ブリューアス様と協働で、新サービス「LINEヤフーテックアカデミー × DX BOOSTER共同プラン」を立ち上げました。
本記事では、この新サービスに込めた思いとともに、AI時代の働き方や求められるスキルセット、組織の変革について、デジタル人材育成をリードする3社の鼎談をお届けします。
■LINEヤフーテックアカデミー
Yahoo! JAPANやLINEを運営するLINEヤフーと、累計30,000人、1,000社以上の確かな教育実績を持つブリューアスが合同で設立したオンラインスクール。LINEヤフーテックアカデミーの企業研修は、大手企業やLINEヤフー社内の研修で採用されている。
https://ly-academy.yahoo.co.jp/tech/
■LINEヤフーテックアカデミー × DX BOOSTER共同プラン
2025年5月19日より提供を開始した、生成AI活用によるマーケティング業務の効率化を支援するプラン。e-learningと個社別ワークショップ型研修を組み合わせ、企業の生成AI活用人材を基礎から業務活用まで一気通貫で育成。これにより、データ分析、企画提案書の作成、コンテンツ制作などのマーケティング業務の効率化と生産性向上が期待できる。
▶︎参考データ(当社調べ)
【調査レポート】DX推進は進むが、人材育成は後手。「経営層の意識」と「現場の実態」のギャップが浮き彫りに
対談メンバー

谷口 美明 氏
LINEヤフー株式会社
LINEヤフーテックアカデミー プロダクトオーナー
人事総務CBU ピープル・デベロップメントユニット 人材開発ディビジョン Divリード
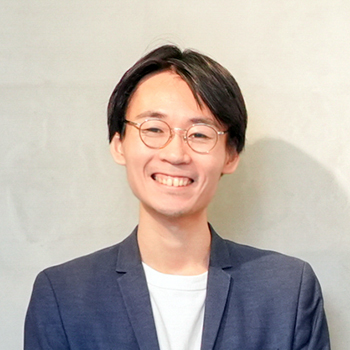
藤田 大輝 氏
株式会社ブリューアス
法人事業部
ビジネスマーケティング

杉山 健太
シナジーマーケティング株式会社
DX事業部 部長

鈴木 英利佳
シナジーマーケティング株式会社
DX事業部 コンサルタント
※部署名・役職は取材当時(2025年10月)のものです
AIは「わからないから使わない」から「使わないと損」なツールへ|ビジネスの現場で起きている意識変化
―― 最初に、今回の取り組みが始まった経緯をお聞かせください。
ブリューアス 藤田:
LINEヤフーテックアカデミーで、マーケティング職に特化した法人向けの「生成AI活用コース」をリリースしたことがきっかけです。研修内容をより充実させるために、マーケティング領域の専門企業との協業を模索していた際に、シナジーマーケティング様とご縁がありました。
シナジーマーケティング 杉山:
弊社も人材育成サービスを展開しており、「日本企業のさらなる成長を促すためには、AI教育とマーケティング実務への支援が不可欠」との考えが一致し、今回の共同プラン提供へと至りました。
LINEヤフー 谷口:
今回の協業で、「企業組織全体に広がるAIリテラシー不足」を解決したいと考えています。AIの利便性は理解しているけれど、実務で使いこなせないというギャップがあり、結果として、活用指針や育成が不十分なまま、現場任せになっている現状があります。これらを解消し、「AIで業務プロセスを変革し、成果を最大化できることが当たり前」という文化を定着させるためには、マーケティング現場に寄り添った実践的なプログラムが必要でした。

―― 「AI教育とマーケティング実務支援の提供が重要」と考えた理由をお聞かせください。
シナジーマーケティング 杉山:
デジタル化の加速によってマーケティング活動は複雑化し、労働人口の減少という課題も深刻化しています。この状況を乗り越えるには、AIで業務を効率化し、人間はより戦略的かつクリエイティブな業務に注力することが不可欠です。マーケティング担当者においては、「AIを使いこなして業務効率化を図る能力」だけでなく、「AIのアウトプットを成果につなげる実践力」が要求されます。
多くの企業がこの重要性を理解し、AI活用に意欲を示す一方で、実際に一歩を踏み出せない企業も多いのが現状です。その背景には、「AIの具体的な活用方法や成果への貢献度が不透明」という課題が存在します。
―― 帝国データバンクが2024年6月に実施した「生成AIの活用状況に関する企業アンケート」によると、「生成AI活用は17.3%にとどまり、半数以上が人材・ノウハウ不足に懸念」とのことですが、活用の障壁を乗り越えるためにはどのようなアプローチが適切でしょうか。
シナジーマーケティング 杉山:
実際に、現場の「『AIは使いこなすのが難しそう』『従来のやり方で十分』などのネガティブな声がネックになり、AI活用が思うように浸透しない」という声はよく聞かれますね。これを乗り越えるためには、経営層によるトップダウンでのリードが不可欠です。現場レベルでは、AIを使うことによる小さな成功体験を積んでいくことが効果的だと考えています。
ブリューアス 藤田:
そうですね。導入がなかなか進まない背景の一つとして、新しい技術への苦手意識が挙げられます。スマートフォンが登場したときに、フィーチャーフォン(ガラケー)からの移行に抵抗を感じた方も多かったのではないかと推察します。しかし、今では普通にスマートフォンを使っていますよね。AIも同じ流れで普及するのではないかと予想しています。
杉山さんがおっしゃったように、「使ってみると意外と簡単」「思ったより便利」と気づくこと、つまり小さな成功体験を得ることが最初のステップになります。
シナジーマーケティング 鈴木:
そのため、共同プランではAIを業務に使い始める「きっかけづくり」を重視しています。メールの添削や提案書の骨子を考えるといった身近な作業から始めることで、「よくわからないから使わない」という考え(先入観)を取り払うことを最初のステップとして設計しています。
スマートフォンが起こした変革の再来!人とAIの共創でビジネス現場はどう変わる?
―― AIの普及は「スマートフォンが登場したときと同じ流れをたどるのでは」とのお話がありましたが、具体的にビジネスの現場はどのように変わっていくと予想しますか。
LINEヤフー 谷口:
根本から変化すると予想しています。「既存の業務フローやプロセスの一部をAIに置き換える」ではなく、「AIの活用を前提とした業務プロセスを構築する」ことが当たり前になるのではないでしょうか。具体的には、「この〇〇の作業をAIに任せよう」といった発想から、「AIに任せる工程は〇〇まで、人間は上流工程の〇〇を担当」という発想に変わり、人間はより創造性の高い業務や重要な意思決定に集中することが求められると考えています。近い将来、このような視点で業務プロセス全体を見直すことになるでしょう。
ブリューアス 藤田:
業種問わず、業務遂行やそれに伴うPDCAのスピードも大きく向上すると予想しています。マーケティング職や営業職を具体例として説明すると、企画書や提案書、報告書などの資料作成に時間がかかりがちですが、まずAIで80%くらいまで土台を作ります。それを担当者がチェックして上司やお客様に提示し、方向性の合意が取れたら、残りの部分を再びAIを活用しつつ専門知識を組み合わせて仕上げる、といったことが可能になります。これにより、業務効率だけでなく品質も格段に向上すると考えています。

シナジーマーケティング 杉山:
マーケティング領域でもう一つ例を出すと、LP(ランディングページ)やコンテンツなどの制作業務も高速化・低コスト化すると予想しています。専門企業に依頼すると1週間かかる制作も、AIを活用してある程度まで土台を作ってから人間が調整することで、即日かつ自社のみで完成させることが可能です。節約できた工数や制作コストを新規施策に振り分けることができるので、PDCAサイクルも加速します。その結果、業務プロセス全体の無駄がそぎ落とされ、成果が最大化されやすい「筋肉質な組織」が実現すると考えています。
シナジーマーケティング 鈴木:
従来は専門職でないと手がけられなかった領域も、AIを活用することである程度まで対応できるようになると予想しています。特に、施策や提案の事前調査や検討にかかる時間が大きく圧縮されます。例えば、バイブコーディング※1によってエンジニアでなくともアプリやサービスを作って検証ができたり、デスクトップリサーチ※2であればリサーチャーに頼らずともAIで調査できるなど、実施可否の判断や着手までのスピードが格段に上がります。
シナジーマーケティング 杉山:
少子高齢化による労働人口の急激な減少という課題に直面している日本では、単なる効率化を超え、AI活用は持続的な企業存続のための必要条件となりつつあります。AI活用による一人当たりの生産性向上は待ったなしの状況です。
帝国データバンクの調査でも「人材・ノウハウ不足が障壁」とされていますが、これは裏を返せば、「AI人材の育成こそが、日本企業がグローバル競争において生き残るための重要な『攻めの投資』」であることを示唆しているとも言えます。この危機を機会として捉え、AIを前提とした新しい働き方をいち早く組織に組み込むことが、企業が勝ち残るための分水嶺になるのではないでしょうか。
―― お話を聞いていると、ただデジタル技術を導入するだけのDXでは不十分で、AIを活用した業務プロセスの変革(AX※3)を先に考慮しておかないと、結果的にDXのやり直しに迫られる危険性がありますね。
LINEヤフー 谷口:
おっしゃる通りです。現状、DXと言っても、AIをはじめとするデジタル技術を導入するにとどまっている企業が多い印象です。今後は、「DXとは、AIを起点とした新しい業務プロセス、働き方、組織のあり方を追求することである」といった思考に切り替えることが重要です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
※1 大規模言語モデル(LLM)などの生成AIに、自然言語による抽象的かつ対話的な指示を与えてコードを自動生成させる、新しいソフトウェア開発手法。
※2 インターネット上にある既存のデータや文献、公開情報などを収集・分析する調査手法。
※3 DXの一環として、特にAI技術(機械学習、自然言語処理、生成AIなど)に特化して、業務プロセスの高度な自動化、意思決定の迅速化、新たなビジネス価値の創出を目指す取り組み。DXがデジタル技術を幅広く活用するのに対し、AXはAIに焦点を当て、より高度な知的活動や判断を代替・拡張することに主眼を置いている。
AI時代に持続的な企業成長を可能にする、ビジネスマンに必要なスキルセット
―― ビジネス現場の変化に対応するべく、経営層、マネジメント層、現場担当者それぞれに、どのようなマインドやスキルが必要になると考えますか。まずは経営層についてお聞かせください。
シナジーマーケティング 杉山:
経営層は、第一に危機感を持つことが重要だと考えています。AI活用が社内に浸透しなければ、事業が伸び悩み、やがては市場から置いていかれる可能性が高くなります。成果が出る活用方法を検討するのと同時に、いかにして社内に浸透・定着させていくかを考えることが大変重要です。

LINEヤフー 谷口:
私も同様の考えです。経営層は、AI活用の推進・提供に向けたリーダーシップの発揮、AI活用の全社戦略設計力、AIガバナンスへの理解が強く求められます。
特にAI活用の最初の段階では、「経営層が自らリーダーシップを発揮してAI活用を行い、会社としての方針や現場への影響などを考慮したうえで、社員にメッセージを発信すること」が重要です。業務の大部分がAIに置き換わるパターンの職種の方もいるため、メッセージの発信が弱いと、不安が広がり、AI活用への反対の声が上がりやすい土壌が生まれてしまいます。「仕事がなくなるわけではない。定型的な作業はAIに任せ、人間はより創造的な業務に集中してもらう」というビジョンを経営層からはっきり示して不安を取り除くことで、AI活用は浸透・定着しやすくなります。
―― 続いて、マネジメント層についてお聞かせください。
シナジーマーケティング 杉山:
マインド面では、決して逃げずに新しい技術に向き合い、柔軟に吸収することが重要です。現場担当者へのAIの浸透・定着に向けた意識付けや体制構築を行う必要がありますので、それを自覚して行動することが求められます。
シナジーマーケティング 鈴木:
スキル面では、「AIの生成結果を見極める判断力」が求められます。「実現可能性がごく低い手法」「オリジナリティのない文章(著作権違反)」「誤った情報」などがしばしば含まれるので、マネジメント層はそれらを見抜き、正確性と品質を担保するための「審美眼」が不可欠です。
―― 現場担当者はいかがでしょうか。
シナジーマーケティング 鈴木:
マインド面では、「上司に言われたからやる」ではなく、「成果を上げるため、ひいては自身のキャリアのためにやるべきこと」として捉え、率先して活用する姿勢が重要です。スキル面では、普段の業務に積極的にAIを取り入れ、効率的かつ品質の高いアウトプットを生み出すことが求められます。あわせて、AIの生成結果を鵜呑みにせず、人間の手や目を使って情報を精査するスキルも必須です。
ブリューアス 藤田:
ポジション問わず、今後「積極的にAIを活用できるマインド」が求められることは間違いないです。AIツール側のUX向上によって、高度なプロンプトスキルがなくても80点以上の回答が出力されるようになってきています。そうなると、「いかに早くベストプラクティスに到達できるか」が活用の差になっていきます。AIを利用すればするほど、「この作業にはどの指示が有効か」「どの業務をAIで自動化すれば一番コスパが良いか」といった発見がなされ、組織内に蓄積されていきます。比例して、組織全体の工数やコスト、品質が最適化され、PDCAサイクルが加速します。そのために、「積極的にAIを活用するマインド」を持って多くの試行回数を踏むことが大切だと考えます。
3社の知見を結集することで誕生した、「実践と定着」を促す”ワンストップのデジタル人材育成プログラム”
―― AI活用による企業成長をご支援するべく、生成AIをはじめとした先端テクノロジーを、実務で活用できる人材を育成する企業向けの研修プログラム(共同プラン)を提供しています。その特徴や受講効果をお聞かせください。
LINEヤフー 谷口:
単なる「先端テクノロジーの知識・スキル習得」のためではなく、「テクノロジーを活用し、業務改善や新しい価値創出を自ら企画・実行できる人材を輩出すること」を目的とした研修です。研修形式としては、座学による基礎研修と、個社別かつ実務に即した実践的なワークショップの両方を実施しています。日常業務に活用しやすくすることと、学習効果を高めるためには「実践(知識の応用)」と「実験(検証と改善)」を繰り返すことが重要になるためです。
シナジーマーケティング 杉山:
特徴としては、大きく2つです。1つ目は、約1,500人※4のAI人材を育てたLINEヤフー様監修のカリキュラムをベースに、当社が創業以来25年間にわたるマーケティング支援で得た成果の出やすいノウハウをご提供できる点です。
2つ目は、ワークショップのカリキュラムは受講企業様ごとのオーダーメイドのため、そのまま実務に活用しやすいだけでなく、自分事としても捉えやすいため、ノウハウの定着率が高まる点です。ワークショップでは、当社の経験豊富なDXコンサルタントが専属で担当するため、研修にありがちな「ただ学んで終わり」にしない、学んだことが今すぐ現場で使える内容をご提供しています。
ブリューアス 藤田:
具体的には、まずAIの基礎知識を体系的に学べる「e-learning」の基礎研修を受講。続いて、全4日間の日程で、AIの基礎から応用までの実務を、受講企業様の商材をテーマにしたワークショップで体験する「AI活用アカデミア」(生成AIによるデータ分析、提案書作成、コンテンツ作成など)を受講していただきます。
―― 受講することで、具体的にどのような効果が得られますか。
シナジーマーケティング 鈴木:
短期的な効果としては、生成AIを活用する際に最初のハードルとなる「よくわからないから使わない(使えない)」を突破し、生成AIを業務に使う習慣を身につけられます。具体的には、資料作成やデータ整理、メール作成などの日常業務に対して、AIを「業務効率化の道具」として活用できるようになります。主な成果は、業務遂行スピードや品質の向上です。

ブリューアス 藤田:
長期的には、研修によってAIを業務で使う頻度が増えることで、組織内のナレッジ共有が活発化し、より高度な活用方法が生まれるサイクルの構築が狙いです。このサイクルを生むために特に重要なのは、業務効率化を進めた先に起こる個人の「意識と行動の変化」です。従業員一人ひとりが常にAIの活用方法を考え、率先して実行・改善するマインドが醸成されることで、AIで成果が出るまでのスピードが格段に速まります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
※4 LINEヤフー社が提供する「AI活用アカデミア」の2024/10/9時点の延べ受講者数。
一歩を踏み出すときは今!デジタル人材育成は、未来の企業競争力確保への先行投資
―― ビジネス現場でのAI活用が当たり前の時代において、どのような人材が求められるようになると考えていますか。
LINEヤフー 谷口:
デジタル人材の定義が一昔前の「エンジニア」から「AIを使いこなせる人材」へとシフトしたことで、人材育成の焦点もAIを「作る側」から「使う側」へと移行しつつあります。今後は、AIを効果的に活用するための「問いを立てる力(イシュー設定力)」と、課題解決に向けて「ビジネスモデルや業務プロセスにAIを組み込む力」を持つ人材が重宝されると予想しています。
シナジーマーケティング 鈴木:
谷口様のおっしゃる通り、デジタル人材の価値はAI活用を前提とした「業務への組み込みと成果の最大化」に移行すると考えています。これは経産省の「デジタルスキル標準」のアップデートも示す通りです。将来的にAIがさらに進化すれば、人間はAIと知識を相互に高め合い、社会を活性化させる役割を担うことになります。この進化に乗り遅れないよう、「いかに適切にAIを事業に組み込むか」を思考できる人材の育成が急務です。
ブリューアス 藤田:
AIの浸透によって企業間の差別化が難しくなるほど、「問いを立てる力とその試行数」の重要性が高まります。差別化の鍵は、企業が持つ「独自の知見やノウハウ(ドメインナレッジ)」を、いかにAIに取り込み、適切な問いを立てて活用できるかです。ビジネス現場では、この知見とAIを掛け合わせて「新しいビジネスモデルを設計できる人材」が強く求められると予想しています。
シナジーマーケティング 杉山:
AIによるアウトプットが大量に生み出される時代において、生成された情報が本当に正しいかを見極めるファクトチェック能力も極めて重要になります。情報セキュリティやコンプライアンスといった新たな課題への対応も含め、この情報爆発時代に適切に対処できる人材の育成が急務だと考えています。
―― 続いて、ビジネス現場へのAIの浸透によって新たに生まれる世界と、そこで大きく成長できる企業像についてお聞かせください。
LINEヤフー 谷口:
新たに生まれる世界観についてお話しすると、ビジネス現場へのAIの浸透によって、人間の役割はより明確になります。AI活用を前提とした業務プロセスでは、問いを立てる段階でテーマを与え、そのアウトプットが適切かどうかを判断するといった人間の関与が不可欠です。AIに置き換わる業務領域が増えるほど、人間は本来集中すべき創造・判断・戦略といった上流工程の業務に専念しやすくなります。結果として、職種によらず、誰もが創造性を発揮し、膨大なデータに基づいた迅速かつ高度な意思決定が可能な社会が実現すると予想しています。
ブリューアス 藤田:
AIのアウトプットだけでは、いずれ企業間に差がつかなくなると予想できるので、各組織が持つドメインナレッジをいかにしてAIに組み込み、活用するかが、ビジネスのスケールの成否を分けます。そこに正面から取り組むことができる企業が成長すると考えています。
シナジーマーケティング 杉山:
企業活動の目的はAIを使うことではなく、事業成果を上げて企業価値を提供することです。今後大きく成長できる企業は、AIを目的化せず、「自分たちが解決すべき課題」にフォーカスしたうえで、AIをリソースとして適切に活用しつつ事業を推進できる組織だと考えます。

―― 最後に、AI活用をご検討中の企業様へ、ぜひメッセージをお願いします。
LINEヤフー 谷口:
仕事のあり方は、今まさに大きく変化する過渡期にあります。技術が複雑になる前にAIを業務プロセスのベースとして組み込む経験を積むことが、将来の競争力を確保する鍵です。着手するなら、今が最適です。まずは、知識の基礎固めやメール作成などの業務のごく一部をAIに任せるなどの「小さな一歩」から始めてみてください。小さな成功体験が、やがて組織全体の大きな変化へとつながります。「今からでも遅くない」ことを実感していただき、未来をともに切り拓いていきましょう。
ブリューアス 藤田:
「AIに苦手意識がある」「慣れたやり方を変えるのは面倒」と感じるのは自然なことです。しかし、この壁を突破しなければ、近い将来に市場から取り残されてしまいます。AI活用では、知識習得だけでなく「使ってみたら意外と便利だった」という小さな成功体験が重要です。私たちの研修は「きっかけづくり」と「実務への定着」に焦点を当てており、「AIを業務で使いこなせる自信」を得ることができます。私たち3社の知見を結集したプログラムでしっかりご支援しますので、「AI活用という未来への投資」をぜひご検討ください。
シナジーマーケティング 鈴木:
AI導入の成果は、単なる効率化で終わりません。成果を実感することで、従業員一人ひとりが「もっと高度な活用はできないか」と自発的に考えるようになります。この意欲の向上が、組織全体のPDCAサイクルとイノベーションを劇的に加速させる原動力です。誰もがイノベーションに挑戦できる世界の実現を目指して、全力でサポートいたします。
シナジーマーケティング 杉山:
AIは、企業が未来を築くための「最大の武器」です。単なるツールではなく、「人間と知識を高め合い、創造性を解放するパートナー」として捉えられるかどうかが、今後の企業の命運を分けます。この変革には、経営層の強い覚悟が必要です。私たちは研修プログラムを通し、貴社のビジネスを次のステージへと進化させるご支援をいたしますので、ぜひご検討ください。
(取材/編集:経営推進部 ブランドマネジメントチーム)